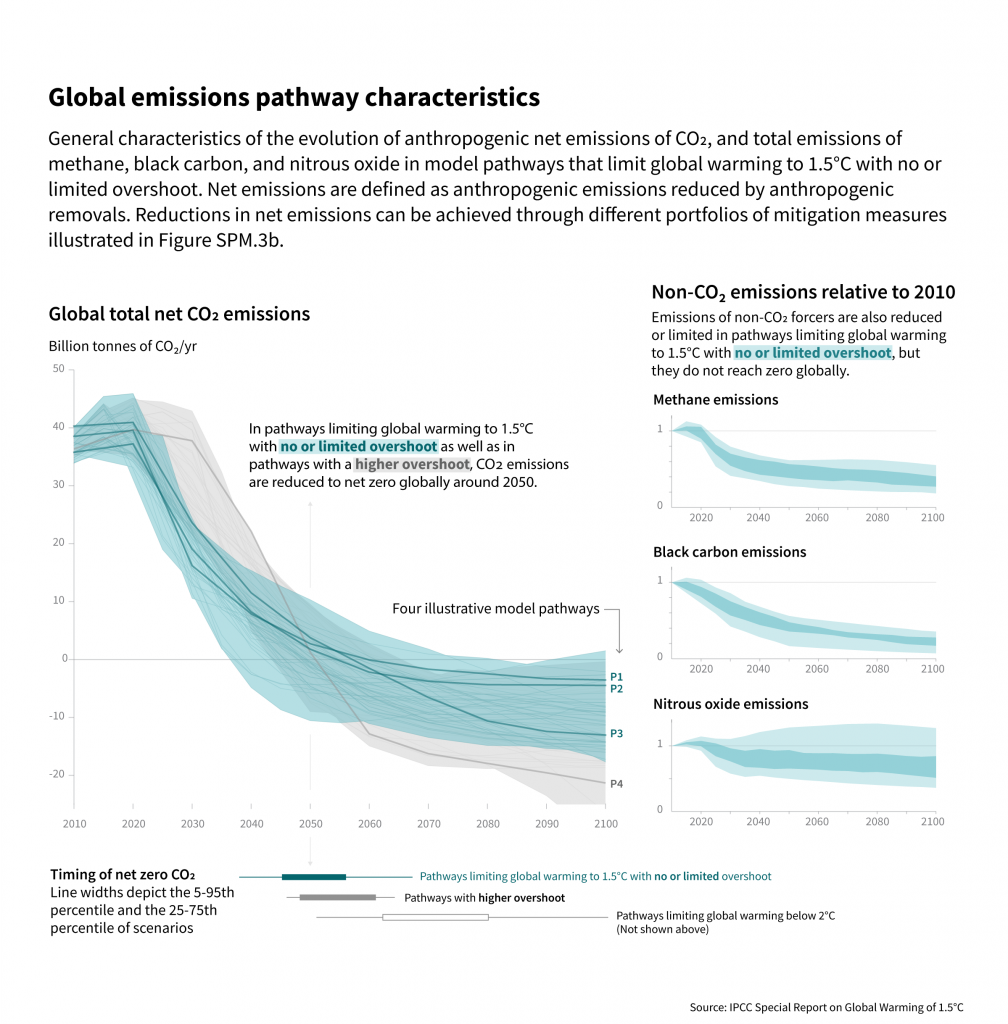新型コロナウィルス感染症についてまとまった知識を得るためにぴったりの一冊である。参考文献も多く載っていて便利である。本書を読むと、流行が始まってかなりの時間がたち、この感染症について相当いろいろなことがわかってきたと思う。
新型コロナウィルスは以前流行したSARSやMERSと似たウイルスだが、毒性はそれほど強くなく感染しても8割が無症状あるいは軽症で推移する。この点がSARSやMERSに比べて世界的流行となった最大の原因である。残りの2割は肺炎症状を示しさらに数パーセントが人工呼吸を必要とする重症に移行する。重症化のリスクは、男性、高齢、肥満、基礎疾患持ちであれば高くなることがわかっている。
感染ルートは飛沫感染と接触感染が主なものであり、このため「三密」環境を避けてマスクと手洗いすることが有効な感染対策となる。軽症の治療薬はウイルスの増殖を直接防ぐような決定的なものが無いので、これがインフルエンザとの大きな違いとなっている。重症になった場合は炎症つまり免疫の暴走を止めるという観点からいくつか有効な治療薬が出てきている。重症に関しては1年の経験を経てある程度治療法が確立してきたようで、致死率は5%から1-2%まで低下してきた。最新鋭のワクチン技術により遺伝子情報をもとに迅速にワクチンが設計、製造できるようになったことは大きな進歩であり。現在は世界中でワクチン投与が始まっている。
感染は1年以上前に武漢周辺から広がった。ウィルスはコウモリ由来である。武漢ウイルス研究所では緩い隔離レベル(BSL2)でコウモリのコロナウィルスが研究されていたことは事実である。日本では2020年2月に武漢由来のウィルス流行が収まったが、3月に入りもっと感染力の強いヨーロッパ型のウィルスが流入しその後変異を繰り返して流行を拡大させた。ただ、欧米に比べ、ロックダウンのような厳しい政策をとっていないにも関わらず感染者数も死者数も格段に少なく、主に遺伝的要因の可能性が指摘されている。
と、ここまで本書は多くのデータを整理し今わかっていることを手際よくまとめている。最終章は「そして共生の未来へ」として今後の展望について触れている。ウィルスと「共生するための医療システム」として「病院と介護施設の患者と職員への院内感染対策が重要」であり、その基本は「定期的なPCR検査」であるという。これまでに明らかになったウィルスの特徴をふまえればこうしたピンポイントの対策は効果的だと思う。
さらにウィルスと共存し、経済を回すためには「すべての人がPCR検査を受けられるようにすることである」という。これについてはPCR検査が、偽陰性となる確率が25%、偽陽性となる確率が0.8%となる特性をもっていると考えると、どうかと思う。陰性確認を目的とした、社会の安心と安心のための大規模なPCR検査はかえって混乱を招くと思う。
あとは、「感染症と経済への対策は両立できる」としてGDPの減少と死者数の関係(図13-1, 本書p294)を論じ、「コロナをコントロールできない国は、経済の痛みも大きい」とする。現在、国内の製造業はほぼコロナ前の水準に戻っており、供給という観点からみればインフレになるような懸念もなく、あとはサービス業の復活を待つばかりとなっている。今のうちに「共生するための医療システム」を整えコロナをコントロールして需要が出てくれば、サービス業も復活してくるだろう。最近の株価の上昇も今後の楽観的な予想があってのことではないかと思う。逆に言うと、増税など需要を減らすような経済政策はとても危険だ。